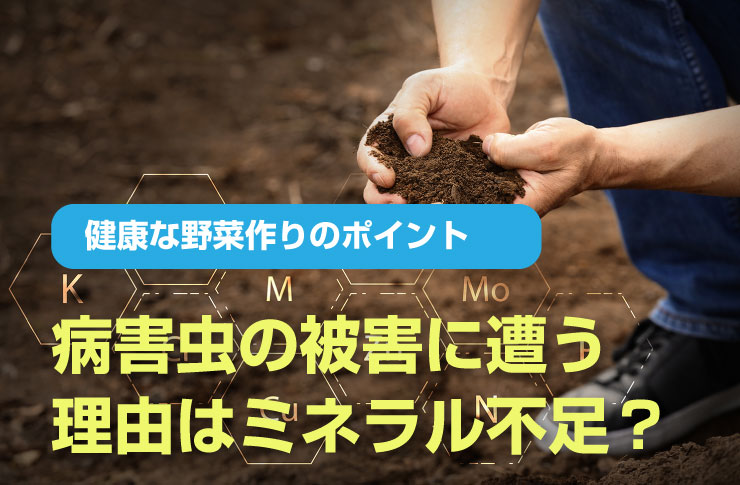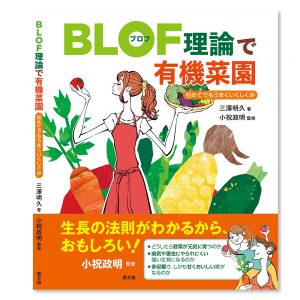葉の緑色をつくる素「マグネシウム」
こんにちは。三澤です。
野菜を良く育てるために必要な肥料、養分の解説シリーズ、今回は「マグネシウム(Mg)」です。
マグネシウムは光エネルギーを捉える元素で、光合成を行う葉緑素(クロロフィル)の中心にあるミネラルです。
マグネシウムがなければ光合成が出来ず、葉の緑色も作られません。
十分な日光があっても光合成能力が落ちてしまいます。
また、マグネシウムにはリンの移動を促進する働きもあり、さまざまな酵素を活性化する役目も担っています。
マグネシウムは葉緑素の材料であるだけでなく、二酸化炭素の吸収、炭水化物の合成や、ATP(エネルギーを貯める物質)の合成にも深く関わり、野菜にとって、なくてはならない重要なミネラルです。
マグネシウムの欠乏症
マグネシウムは、カルシウムと同じで、雨水などによって、土壌から流亡しやすい要素です。
マグネシウムは植物の体内を移動しやすいミネラルで、リンと同様、生長点や新芽、花芽など、細胞分裂の活発な場所に集まるため、欠乏症は下の古い葉から黄色くなるという症状であらわれます。
マグネシウム欠乏の特徴は、葉脈の緑を残して葉色が黄色くなることで、他の要素の欠乏の時とは違いが明確です。
マグネシウム欠乏は、生育の初期にはあまり見られません。
カラダが生長して大きくなり、花や果実をつけるようになると欠乏症が見られるようになります。
トマトでは、果房の中間のところの葉の葉脈間が黄色くなり、葉が内側に巻くといった欠乏症が見られるようになります。
ダイコンやカブでは、根の肥大が始まるころからマグネシウムの欠乏症が出やすくなります。
果菜タイプの収穫量を増やそうとする場合、カリを多くする傾向がありますが、カリが多すぎるとマグネシウム欠乏の症状を起こします。
カリを優先して吸収し、マグネシウムが土中にあっても吸収できず、結果、マグネシウムが欠乏してしまうからです。
またマグネシウムが不足すれば、リン酸が生長点に運ばれなくなり、生育が落ちます。
反面、マグネシウムが十分にあると、リン酸の吸収が良くなります。
これは逆も同様で、マグネシウムが十分にあっても、リン酸が足りないとマグネシウムの吸収が悪くなります。
マグネシウムとリン酸は、どちらもその吸収に相乗作用があります。
![]()
マグネシウムの過剰症
通常、マグネシウムそのものの過剰障害はあまり見られません。
マグネシウムが過剰になると、土壌のpHが高くなり、カルシウム、カリウム、また鉄やマンガン、亜鉛、ホウ素といった微量要素の吸収が阻害され、各要素の欠乏症が出るようになります。
マグネシウムが極端に多い場合、下位の葉がまだらに黄化し、やがて褐色の斑点を示すようになります。
バラ科のイチゴでは、マグネシウム過剰は葉に黒い斑点があらわれることがあります。
ただし、それほど極端な過剰でない場合は、症状で見分けることは難しく、土壌分析によって判断することがもっとも有効です。
鉄欠乏、マンガン欠乏、カルシウム欠乏といった症状が出た時、実はマグネシウム過剰にによって、それらの症状が出ている可能性があります。
関連記事
以下の記事では、野菜にとっても人間にとっても、なければ一瞬も生きられない様々なミネラルについて解説しています。
併せてお読みください。
イラスト制作のお問い合わせ・ご依頼
お仕事のご依頼・お問い合わせはメールフォーム、またはお電話により受付ています。
お気軽にお問い合わせください。